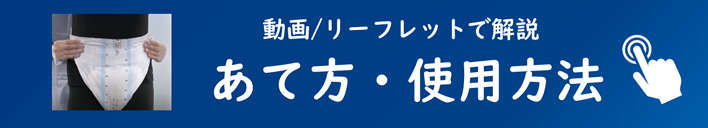コンチネンスケアwith TENA 処方事例集
Nr.03

体調変化による安静期から自立歩行回復に寄り添った事例
「Omsorg för Alla」は、「みんなのケア」を意味するスウェーデン語です。「Omsorg」には、「相手の尊厳や思いを大切にした継続的な思いやり」という意味が込められています。本紙では、TENA を活用して、すべての人の「尊厳(Dignity)」を大切にするケアを実践しておられる「ケア処方事例」を紹介します。
ご利用者プロフィール
Bさん(女性)88 歳 要介護度4。急性腰椎症の治療のため入院。在宅復帰困難となり、施設に入居されました。昔は、友人と美容院で働いて生活されていました。入居後に体調を崩したことで転倒。疾患による酸素濃度低下により、在宅酸素療法が必要となり、安静を要して車いす使用に。以前のように自身でトイレに行くことができなくなり、落ち込みが見られていました。

些細なことがつまずきのきっかけに
失敗感を取り除くことで気分の落ち込みゼロへ
元々「TENA コンフォートミニエクストラ」を使用し、トイレで排泄していたBさんは、体調不良をきっかけに転倒し、疾患による酸素濃度の低下で安静が必要となり、室内だけでの生活となりました。介助量が増えた頃、失禁も多く見られるようになったことで、ご本人は「私は何もできなくなった」「もう生きている価値がない」などと話すようになり、激しい気持ちの落ち込みもありました。そこで安心感を持たせるために、パッドの変更を検討しました。確認していくうちにTENA コンフォートミニエクストラでは吸収しきれない尿量だったのでTENAコンフォートスーパーにランクアップ。尿漏れの不安を取り除き、「夜間はこれで大丈夫ですよ」と説明することで、安心感をもって療養期間を過ごせるようにしました。Bさんはしっかりとした性格なこともあり、失禁してしまうことに対する失敗感が強く表れていました。しかし、TENA は吸収性能が高いため、失禁してもすぐに濡れた感覚を感じずしっかり吸収するので、失敗感が薄れました。
歩く提案で変わる生活リズム
トイレで座れる安心感
TENA コンフォートスーパーに吸収ランクアップしたことで失禁による尿漏れが気にならなくなり、ご本人も少しずつ元気を取り戻していきました。転倒する前は普通に歩かれていたBさんでしたが、安静のために車椅子を使ったことにより活動量が少なくなっていました。Bさんの様子を観察していたスタッフから「キャスター付きピックアップ歩行器に切り替えられるのでは」という声が上がったことをきっかけに、まずは室内の移動を歩行器で行うよう勧めました。
ご家族からは、「酸素吸入器を繋いでいるから無理しないでいい」とは伺っていたものの、介助量を減らして自立することがご本人の生活レベルやリズムを整えることにもなります。とはいえ最初はご本人も積極的ではありませんでした。元気を取り戻してきてはいたものの、当初は立つ意思があまりありませんでした。それでも「やってみよう」と声をかけ続け、少しずつできたことを褒めて、ステップを踏むことで歩行器を使って歩き、トイレにも行けるまでになりました。
その結果、活動量が増えたことで排泄リズムが元に戻り、酸素吸入器も取り外せるまでに回復。室内移動からフロアへと歩行距離をのばし、活動量を上げることができました。失禁も減り、TENA コンフォートミニエクストラで生活ができるようになりました。療養期間中は尿意も便意も感じられず、それがご本人にとって非常に辛いことでしたが、今では尿意と便意も戻り、トイレに座って排泄する喜びを取り戻して、生き生きと過ごしています。
排泄の失敗から始まる悪循環
自信喪失をいかに防ぐか
認知症状がなくしっかりしている方ほど、排泄の失敗は落ち込みの原因になります。それは気持ちをふさぐだけでなく、交流や活動を減らし、生活リズムを不安定にさせ、悪循環に陥らせます。Bさんはまさにそうでした。スタッフにとっては入居者様の排泄の失敗は恥ずかしいことでも、失敗でもありませんが、ご本人にとっては大問題です。
うえよなばる様では、できることを前提に失敗してもいいから、やりたいこと、できそうなことには挑戦してもらうことを基本としています。できることをできないままにしておかないことが、自活への一歩となります。
見守り誉めて励まして
本人の気持ちを「できる」に向ける
うえよなばる様では医療チームと連携し、病気の療養期間中でもできるだけ普段の生活に近づけるよう工夫をしています。様子を見ながらですが、療養が終われば、活動量を取り戻す訓練を始めます。「病人気分」になって自信をなくし、訓練や活動をしたがらない方でも、できることを褒めたり、励ましたりすることで気持ちが変わってくることがほとんどです。
励ましを繰り返すうちに、期待に応えたい、ご自身ができることは自分でしたいと思ってくれるようになり、それぞれの方なりに一生懸命頑張ってくれるようになります。少しのことでもできたら「できましたね! すごいですね!」と誉めて励ますことをポイントにスタッフ総出で応援しています。
ご本人ができないと言うなら、寄り添って手助けする。一緒にできそうなことを考えて、やってみる気持ちになるよう誘導することが大事です。
「怪我をさせてしまったら」と思い、安全を優先する意識が強くなりすぎると無理をせずに現状維持を優先させてしまうことも多くなりがちです。そうではなくそれぞれの方を信じて、できることは自分で行う生活を一緒に取り戻そうという姿勢で取り組むことが、入居者様自身が「できる」自分を信じられるきっかけになると考えています。

よりよいケアを職員の共通認識に
ご本人やご家族の理解も重要
元々社交的な方でも、できないことが増え、気持ちが落ち込んでいくうちに必要なケアを拒否する傾向が出る方もいらっしゃいます。Bさんも当初は歩行器を使って歩きたがらなかったのですが、継続した励ましとTENA コンフォートスーパーに切り替えて安心感が増したことがきっかけで、歩けるようになり、在宅酸素も取り外せるようになりました。
入居者様が抱えている課題の対応策を、ご本人の視点に立って真摯に考えるためにはまず、本人の様子をしっかり観察することが大切です。
入居者様は一人ひとり体格も、性格も、体調も違います。
急に立ち上がることの意味、ソワソワする挙動などが何を意味しているのか、各スタッフは日ごろからしっかり観察して記録するようにしています。
そうすることで、スタッフ同士での情報共有に活用できるほか、同一行動時の照合、考察にも使えます。記録の際には、トラブルはもちろん、入居者様が発言した言葉もそのまま記載し、共有しています。
また、スタッフ同士でも、悩んだり困ったりしたことがあれば気軽に相談し合うようにしています。入居者様に向ける意識と同じように、失敗を恥ずかしいこととせず、隠さずオープンにして対応策を一緒に考えています。
気軽に相談できる環境を作り、各スタッフが良いと思うことを実践して、わからないことがあればやって見せる。このステップがあることで入居者様もスタッフを信頼できるようになり、「できない」自分から「できる」自分になれるのです。そうして活力を取り戻した入居者様の言葉も、施設としての姿勢もご家族に報告しています。
ご本人を心配し、ご家族から「そこまでしなくていい」とお言葉をいただくこともありますが、本人ができるならば全力で支えることを約束して、受け入れていただいています。
介護に唯一の答えはありません。
だからこそ挑戦を繰り返しながら、ご家族や入居者様と学んだり笑ったりする日々を楽しむ。しらゆりの園グループの皆さんが大切にしている姿勢です。
私にとってのDignity

尊厳とは、「入居者さんご本人がどう生きたいか、どうしたいか」を聞き、実現していくことに集約されると思っています。それを第一に私たちが提供するケアプランを立て、ご家族に同意をいただいて実践していく。そのことにつきます。
ご家族から「危険なのでこうしてほしい」「スタッフの手間になるからそこまでやらなくていい」という声が寄せられることももちろんあります。しかし危険性だけに目を向けると、どの方も全介助になってしまいます。それでは意味がありません。それに、ご本人が自分でできることが増えれば、スタッフの手間も減ります。ご家族には、その基本的な考え方と具体的なサポート内容をしっかり伝えるようにしています。ご本人の状態に変化があれば、それもご家族に説明します。その積み重ねによって信頼関係を作ることも、尊厳を守るために重要なことだと考えています。

株式会社Health & Wellbeing
うえよなばる介護付有料老人ホームしらゆり(沖縄県島尻郡与那原町)
社会福祉法人立命会では、特別養護老人ホームしらゆりの園で築いたケアメソッドを同グループ内の事業所に展開し成果を上げている。うえよなばるでは2022年の開設時からTENAを使用。