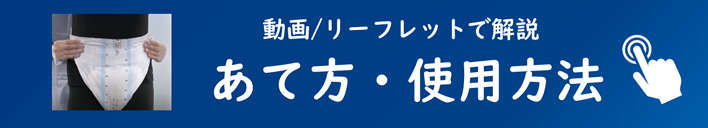コンチネンスケアwith TENA 処方事例集
Nr.02

おむつの変更によって運動機能向上と生活改善を実現した事例
「Omsorg för Alla」は、「みんなのケア」を意味するスウェーデン語です。「Omsorg」には、「相手の尊厳や思いを大切にした継続的な思いやり」という意味が込められています。本紙では、TENA を活用して、すべての人の「尊厳(Dignity)」を大切にするケアを実践しておられる「ケア処方事例」を紹介します。
ご利用者プロフィール
A さん(男性)84 歳 要介護度4。在宅生活中、自宅で転倒。骨折入院し、療養されていたが在宅復帰が困難にて昨年12月入居されました。テレビ鑑賞が好きで、面会以外は、居室から出てくることなく、室内で自由に過ごしています。入居当初、車いす使用され、自操可能でした。車いすのブレーキかけ忘れによる尻もちがみられてから、状態観察を行い、つかまり立ち可能、手すりを捕まえての歩行移動可能と評価ができました。そこで室内に手すりを設置し、車いすを撤廃することができ現在もご自身のペースで生活されています。

行動を観察し、傾向や問題点を明らかに
そこからよりよいケアの可能性を探る
食事は自立して行うことができ、車椅子での自走移動が基本のA さんは、排便のみトイレに行かれる方でした。食事に関する問題はなかったのですが、アセスメントの結果水分摂取量が少なかったためこの点を重点的に取り組むことにしました。
また排泄はおむつカバーとパッドを使用していましたが、カバーがじゃまをしてご自身でパッドを当てられないのが課題としてありました。そこでご家族に相談し、「TENA フィックスコットンスペシャル(以下コットンスペシャル)」へ変更することにしました。コットンスペシャルとパッドタイプのTENA コンフォートを使えば、一般的な紙おむつに比べてごわつきや蒸れがすくなく、比較的簡単にパッドを交換することもできます。
A さんも、スタッフがパッドの当て方を教えたところ、すぐに自分でパッドを交換できるようになりました。体調不良時にはナースコールを鳴らしてくれるので、その際はスタッフの皆さんが交換対応をしていますが、自分でできることがわかってからは基本的に「自分でしたい」「自分でできる」と率先してくれています。コットンスペシャルを使用してからは排便以外にも日中にご自身でトイレに行くところが何度か見られるようになりました。それに伴い、頻繁だった失禁も軽減し、コットンスペシャルを使って安心して過ごせるようになりました。
できるかできないかではなく
どうすればできるかを考える
車椅子を使っていた当時、ブレーキのかけ忘れから尻もち事故が多発していたA さん。トイレ利用時にはつかまって立って歩くことができる、踏ん張る力があることがわかったので、自ら歩くよう誘導していくことにしました。
安定した手すりがあればつかまって移動ができることから、室内を自由に移動できるよう、室内の導線に垂直型手すり(バディ)を設置しました。すると大変喜んでくださり、バディを使いながらトイレに歩き、自分のリズムで生活できるようになりました。コットンスペシャルは紙おむつ特有のごわつきがほとんどないため、歩行の邪魔にもなりません。歩行時に違和感がないことが、スムーズに移行できた要因でした。
手すりを使ってつかまり歩きができることで、事故原因であった車椅子に乗る機会もなくなり、より活動的に。ご家族の面会時にも、普段生活している2階から、面会室の1階まで自ら歩いて向かい、ご家族をびっくりさせることもあり、大変楽しそうに過ごされています。ご家族から差し入れられた飲み物なども自ら冷蔵庫に取りに行くことができるため、目標水分摂取量も安定して摂取できるように。歩けるようになってからのA さんの生活改善はめざましく、気難しさのあった性格もだんだんとほぐれてきて、スタッフの皆さんに見せる表情も確実に変わっていきました。
入居当初は自分で歩こうという気持ちが見られなかったA さん。トイレに行けないという理由から紙おむつをつけていました。しかし、その紙おむつが原因となり、歩きづらくなっていました。
コットンスペシャルに切り替え、自分でパッドを交換できるようになってからは、日中はスタッフさんの介助付きで歩いてトイレに行くことが通常となり、はいていても違和感がないことが、ご本人の行動や気持ちを前向きに変化させました。

ケアのために取り入れたものが
自立の壁になることもある
Aさんの場合、転倒原因であった車椅子を排除することで、スムーズに生活リズムが改善されましたが、すぐに解決策がわからない入居者様もいらっしゃいます。また、原因と思われることを取り除いたからといって、すぐにうまくいくことばかりではありません。チャレンジしては失敗を繰り返すうちに、「何が正しいのか」とご本人もスタッフも落ち込んでいってしまうこともあります。
それでも日々入居者様を観察し、原因を推測しては新しい方法を試し、違っていれば他の原因を探って再度チャレンジする。うえよなばる様では、その繰り返しで状況が好転するとの考えのもとコンチネンスケアに取り組んでいます。推測が間違っていたり、うまくいかず試行錯誤したりするのは失敗ではなく、ムダでもありません。すべてはケアを良くしていく過程として捉えています。
つかまり立ちができれば歩ける
できることを前提に接する
自分でトイレに行ける、自分で歩けるという自信は、安心感につながり、自尊心も満たしてくれます。Aさんの場合、自分で歩き、トイレに行くようになるにつれて、職員や周囲の方々にも、以前より心を開き、笑顔を見せるようになりました。
少しでもつかまり立ちができたり、足に踏ん張る力があれば、歩けるようになることを前提にケアを進めていくのが、しらゆり流の共通認識。好きなときになんでもできて、どこでも行けることは、介護が必要になったご本人にとっても喜びにつながります。それでも無理に歩かせるのではなく、一歩ずつできることを増やし、思い通りできなくともできたところまでを褒めて、寄り添いながら進めていく。必要なのは、介助をする相手への特別視ではなく、できたことへの共感です。入居後のAさんの事例で切り替えたことは、おむつの種類と車椅子から手すりでのつかまり歩きのみですが、今までできなかったことができるようになり、自分でトイレに行けるようになったことが、Aさんの生活リズムを整えるきっかけとなりました。
また、手すりにつかまっての歩行はあまり心配のないAさんですが、現在も自立訓練を続けています。できることを継続して伸ばすことは、ご本人の活動の幅を広げることになり、結果的に自分でできる意識をより強く持てることになるからです。
とはいえ放置はせず、一人でできることもちゃんと遠くから見守ります。なににつけても様子をしっかり観察し続けることが大切という認識で接しています。
うまくいったことを誉めて励ます
自信がつけば自分から頑張りはじめる
今では打ち解けてくれているAさんですが、当初は多少気難しい面もありました。排便サポートの際、うるさそうだったり、面倒くさそうだったりする素振りが見られ、「声をかけにくい」とスタッフさんが構えてしまうこともありました。
相手が受け入れてないことを、無理に押し付けても誰も取り合うことはありません。その場合は、相手の難しい雰囲気に対処せず、こちらのペースに引き込むことも必要です。普通に明るく接して、声がけをすることを繰り返していると、最初はけげんな表情だった方でも段々と受け入れてくれるようになります。こうしたらできる、できるのでは、と提案スタイルで接することも必要です。
スタッフさんや周囲の方に対して当たるような様子が見られる場合、多くは環境が変わったことや、自分の体が思うようにならないことへの不安や不快感から周囲の人に「当たっている」だけです。
「それでも大丈夫」という安心感を得られると、本来の姿に近づき、穏やかな表情に変わっていきます。

株式会社Health & Wellbeing
うえよなばる介護付有料老人ホームしらゆり(沖縄県島尻郡与那原町)
社会福祉法人立命会では、特別養護老人ホームしらゆりの園で築いたケアメソッドを同グループ内の事業所に展開し成果を上げている。うえよなばるでは2022年の開設時からTENAを使用。